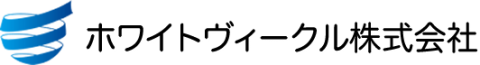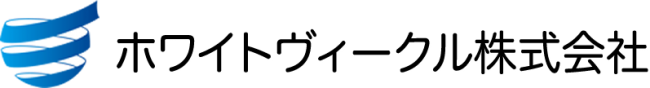利益を出すDPC病院
西日本に、患者別疾病別原価計算を行っているDPC病院があります。すでにすべての患者の疾病別の日々の利益が計算できます。DPC病院は、「診断群分類に基づく1日あたり定額報酬算定制度」をDPC/PPS(Diagnosis Procedure Combination / Per-Diem Payment System)採用する病院をいいます。 包括評価部分と出来高評価部分とを合わせて診療報酬が算定されます。包括評価部分の範囲はホスピタルフィーと呼ばれる基本的費用(施設使用料など)をいいます。出来高はドクターフィー、医師個人の技量を評価する要素が強い報酬で医学管理、高額検査、手術等から構成されます。両者が診療群分類別に決められた、1日当たりの診療報酬額が支払われます。 出来高病院では、請求に歯止めが利かないため米国の制度を模し、創設された制度です。 患者別疾病別原価計算は、患者一人ひとりに要した材料費や労務費、経費を直接費として患者に直課し、患者がどの部門(診療科、病棟)に入院したのかにしたのかを明らかにし、部門別損益計算により計算した間接的に必要となる他のすべての経費を患者に配賦してすべての患者の一人当たり原価を計算する方法です。 その病院の病院全体の一定期間の患者の損益をみると、この病院では患者数でいえば40%以上の患者が赤字で退院しています。金額ベースでいっても近い数字で退院していることが判ります。 患者別疾病別原価計算においては、営業利益ベースにおけるすべての損益を個人個人に割り振られる結果になるので、黒字の患者と赤字の患者の差が病院の営業利益になるというイメージです。 そもそも国の点数の決め方から赤字がでてしますという疾患があります。収益は国の決めた診療報酬で決まるので、あとは原価の大きさにより赤字が出る出ないが決定されます。 この病院は2年前に建て替えをしていますが、建て替え前とでは減価償却費、リース料等の間接費の配賦に4000円以上の原価が増えています。 固定費を外して限界利益でみるということも可能ですが、ここでは常に全部原価で計算をしています。したがって、病棟別にみて間接費の配賦額が異なりますし、また稼働率が高いときと低いときでは、当然稼働率が低いときのほうが、一人当たり患者の固定費の配賦額が増加し一人当たりの利益が減ってしまいます。 月に100人の入院がある診療科(病棟)と200人の病棟では、一人当たりの月額固定費は2倍の差が出てしまいますね。 さて、ざっとですが当院で一人の患者の損益が赤字になる(傾向的)要因を説明します。 1.手術時に時間がかかる 2.多くのオペに直接関与しない医師・看護師が手術に入る 3.在院日数がⅡ期間(DPCでは、入院期間が短くなると診療報酬が下がる仕組みになっています)を超える 4.転棟、退院時期が遅れる(他の病棟への移動や退院が遅れると3に該当します) 5.リオペ(再手術は点数が取れないものもあります)がある 6.感染が起こる(治療コストは請求できません) 7.アクシデントレベル2以上でⅡ期間を超える(3と同様です) 8.アクシデントレベル3b以上でコストが発生する(治療コストは請求できません) 9.クリティカルパス外処方をする(標準から外れた治療によりコストが増大します) 10.他科受診、他病院受診がある(自院に支払い義務があります) 11.入院した病棟稼働率が低い(固定費の配賦が大きい) 12.救急入院が多い(請求できないコストもある) 13.出来高が少ない(高額な検査、オペ等は出来高で多いほど収益はあがる) ただし、患者別利益は、患者数や出来高領域に大きく影響されることがわかります。結局のところ、高密度で質の高い医療を目指す必要があり、短期間での入院、稼働率、増患や退院支援、出来高アップ、生産性向上を行うことが利益を出すポイントであるという結論です。 これらに関する実施事項を列挙し、徹底的に管理することがDPC病院において利益を出すポイントであるということが分ります。...
Continue Reading